COLUMN お役立ち情報
2024/10/21
お役立ち情報
工場の省人化・自動化に活躍する「協働ロボット」。導入のメリット・デメリットとは?
- 協働ロボットの導入メリット、デメリットが分かる
- 協働ロボットを導入する手順やコストがイメージできる
目次
- 協働ロボットとは
- 【メリット】省スペースで、人との分業が可能。誰でも扱いやすい。
- (1)人との協働作業が可能
- (2)柔軟な運用
- (3)安全柵いらず
- (4)専門のエンジニアがいなくてもOK
- 【デメリット】協働ロボットの特性による対応力の限界。
- (1)動きが遅い
- (2)パワーに限界がある
- (3)高価格
- 協働ロボットの導入ステップ
- (1)潜在的ニーズの発掘と課題の明確化
- (2)導入目的の設定
- (3)適切なロボットの選定
- (4)システム設計
- (5)リスクアセスメントと安全対策
- (6)プロジェクト・マネージメント
- (7)導入とテスト
- (8)教育・トレーニング(9)運用開始と評価
- 協働ロボットの導入に必要なコスト
- (1)協働ロボット本体
- (2)周辺機器
- (3)システムインテグレーション (SIer) 費用
- (4)人材教育・育成費用
- (5) 安全対策費用
- 豊富なネットワークを強みに、工場の課題解決に貢献するサンワテクノス。
- この記事を書いた人
- 関連記事
- 関連するメーカー
人件費削減や人手不足の解消、安全の確保や作業における柔軟性といった観点から、工場の様々なニーズに応える存在として、多くの製造現場で導入が進められている「協働ロボット」。この記事では、「産業用ロボット」との違いや「協働ロボット」導入にあたってのメリット・デメリット、必要となるコストや導入手順などについてご紹介します。
協働ロボットとは
協働ロボットは、人間と協力して作業を行うように設計されたロボットです。これらのロボットは、安全機能が組み込まれており、人間と同じ空間で作業することが可能です。協働ロボットは、製造業や物流業、医療分野などで使用され、人間の作業を補完し、生産性を向上させることを目的としています。特徴としては、柔軟性、安全性、簡単なプログラミングなどが挙げられます。
【メリット】省スペースで、人との分業が可能。誰でも扱いやすい。
協働ロボットには様々な導入メリットが挙げられます。
(1)人との協働作業が可能
協働ロボットは、人と同じ作業スペースで安全に作業できるため、生産ラインに並んで単純作業や反復作業を行うことができます。これにより、人とロボットの効率的な分業が可能になります。
(2)柔軟な運用
協働ロボットは移動が容易で、日替わりで作業内容や場所を変更できます。これにより、タクトタイムの超過している作業部分に柔軟に対応できます。
(3)安全柵いらず
安全柵を設置し、作業員との距離を確保する必要がある「産業用ロボット」とは違い、「協業ロボット」は人の安全を考慮した設計となっているため安全柵を設置する必要がありません。そのため、限られたスペースであってもロボットを設置できたり、移動させたりすることも可能です。また、協働ロボットは人がいる空間での作業に用いられるため、特定の製品の製造にのみ使用したり(もしくは使用しない)、作業員と分担して作業を行うことにより、設備費のイニシャルコストが削減できる可能性もあります。こうしたメリットから、特に小ロット・多品種の製造現場などにおいて、協働ロボットは実用的な機器だといえるでしょう。

(4)専門のエンジニアがいなくてもOK
専門のエンジニアがいないから、ロボットの導入にハードルを感じている。そんな企業様も少なくないでしょう。協働ロボットは、ロボット操作に不慣れな人でも直感的に操作しやすいように、機能面の開発も進んでいます。具体的には、ロボットに動作を教える「ティーチング」が専門のエンジニアではない人でもできるようになっていたり、「ハンドユニット」さえあれば、専門業者を呼ばなくても自社でロボットの動作をカスタマイズできるようになっていたり。このように協働ロボットは、特定の技術者だけが扱えるロボットではなく、「誰でも扱いやすい」ロボット。協働ロボットを導入することにより、活用アイデアが生まれたり、生産性の向上が期待できたりと、製造を加速させる起点になるといえます。

【デメリット】協働ロボットの特性による対応力の限界。
「協働ロボット」はメリットだけでなく、デメリットもあります。
(1)動きが遅い
協働ロボットは、人がいる空間で作業し、人に接触しても安全に停止することを前提に設計されているため、「産業用ロボット」よりも動くスピードが一定以下に設定されています。しかし製品によっては、“協働モード”と“産業用ロボットモード”の切り替え機能付きの協働ロボットも開発されており、場面や用途によって使い分けも可能です。センサーと連動し、人が近くにいない場合は“産業用ロボットモード”でスピーディに動作し、人が近くにいたら“協働モード”で安全性を優先する。こうした使い分けにより、安全性を確保しながら作業効率を高めることができます。
(2)パワーに限界がある
協働ロボットの可搬重量は製品によって様々ですが、500g~30kgのものが多く、産業用ロボットに比べるとパワー不足が懸念されます。しかし捉え方を変えれば、これまで作業員が行っていたピッキングや部品の取り付けなど、パワーが必要のない作業については、協働ロボットで代用可能です。近年は30kgの可搬タイプも市場に出回りはじめ、パレタイズ作業にも協働ロボットを活用している事例もあります。
(3)高価格
安全性の確保や、専門性がなくても作業できる使い勝手の良さなど、様々なメリットがありつつも、協働ロボットの普及率は産業用ロボットに比べて低いのが現状です。各軸に力学センサーを内蔵していることから製品が高価格であることも、その一因にあると考えられます。しかし、今後のロボット開発の進歩により、製品のコストダウンや普及率の向上も十分に見込めるでしょう。
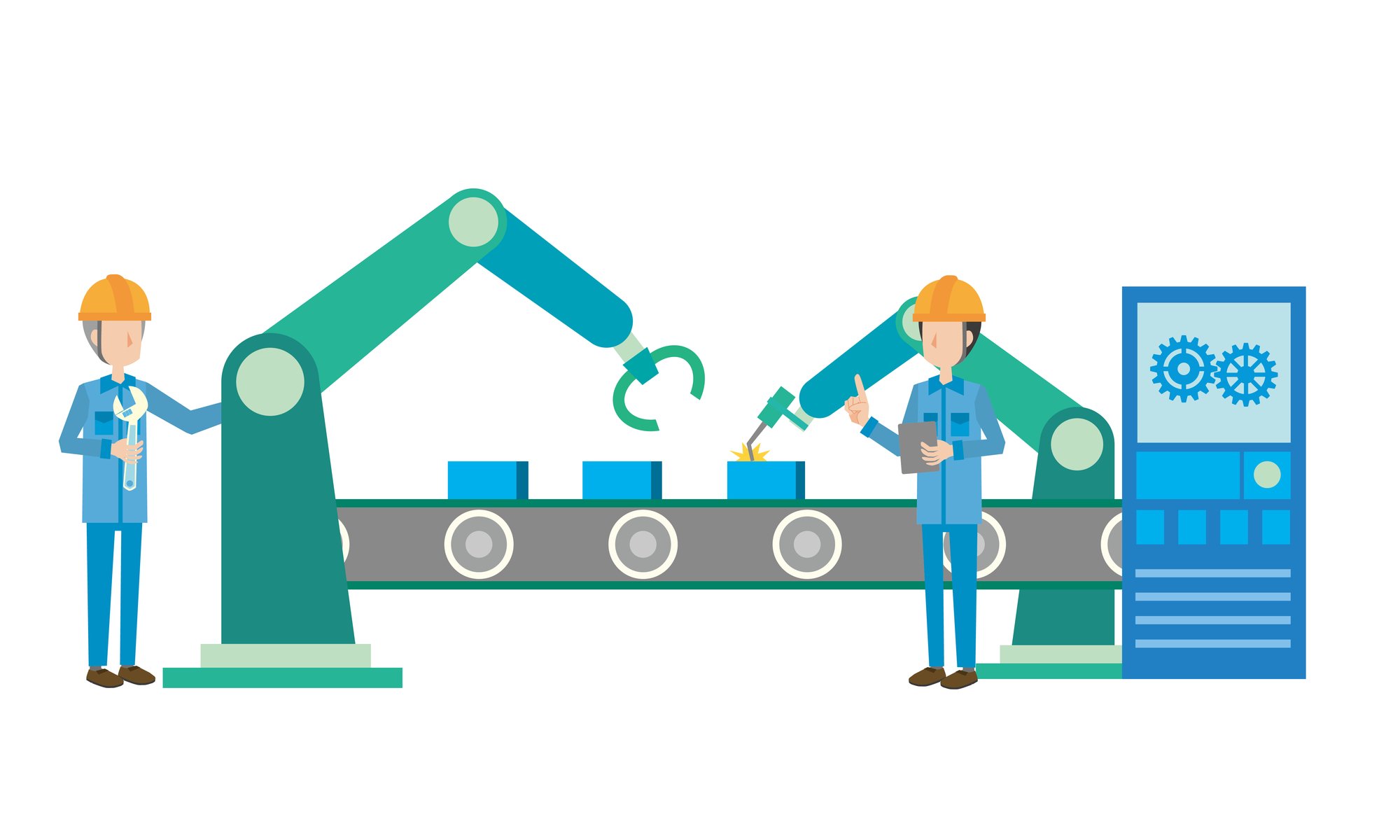
協働ロボットの導入ステップ
協働ロボットの導入にあたり、以下の手順を踏むことで導入が円滑に進みます。
(1)潜在的ニーズの発掘と課題の明確化
現状の作業工程を見直し、潜在的なニーズを発掘します。そして、解決すべき具体的な課題を明確にします。
(2)導入目的の設定
課題に基づいて、協働ロボット導入の具体的な目的を設定します。例えば生産性向上、品質改善、作業員の負担軽減などが該当します。
(3)適切なロボットの選定
業務別のニーズに合ったロボットを選定します。作業内容や目的に応じて、ロボット本体やアームの動かし方などを検討します。
(4)システム設計
ロボット設計、安全設計、周辺設計、制御・センシング設計を行います。これには生産ラインの構築や安全規格に沿った設計も含まれます。
(5)リスクアセスメントと安全対策
ロボット導入により発生するリスクを解析し、必要な安全対策を講じます。
(6)プロジェクト・マネージメント
計画段階から運用開始まで、プロジェクト全体を管理します。
(7)導入とテスト
設計に基づいてロボットを導入し、実際の運用環境でテストを行います。
(8)教育・トレーニング
ロボットを操作する作業員に対して、必要な教育やトレーニングを実施します。
(9)運用開始と評価
実際の運用を開始し、導入目的が達成されているか評価します。
これらのステップを適切に実行することで、協働ロボットの効果的な導入が可能になります。また、初めての導入や専門知識が不足している場合は、ロボットシステムインテグレータ(SIer)のサポートを受けることも有効です。

協働ロボットの導入に必要なコスト
協働ロボットの導入には、本体価格以外にもさまざまなコストがかかります。主に、以下の費用が挙げられます。
(1)協働ロボット本体
一般的に200万円〜500万円程度です。ただし、最近では100万円台の低コストモデルも登場しています。
(2)周辺機器
○グリッパーやセンサーなどのロボットに直接取り付ける装置
○ロボット架台
○ベルトコンベアや加工機などの生産ライン構築に必要な設備
○PLC (プログラマブルロジックコントローラ)
(3)システムインテグレーション (SIer) 費用
ロボットの導入から稼働までをサポートするSIer会社への支払いです。コンサルティング、設計、周辺機器の手配、システムの組み立て、ティーチングなどが含まれます。
(4)人材教育・育成費用
ロボットの操作やメンテナンスを行う担当者の教育にかかる費用。
(5) 安全対策費用
リスクアセスメントや安全装置の導入にかかる費用。
具体的な総コストは、導入する環境や目的によって大きく異なりますが、ロボット本体価格の数倍以上になることが多いとされています。協働ロボット導入の費用対効果は、単純な費用だけでなく、生産性・品質向上などの直接的メリットや、人材採用・教育コスト削減、離職リスク回避などの間接的メリットも含めて、広い視野で検討することが重要です。

豊富なネットワークを強みに、工場の課題解決に貢献するサンワテクノス。
人手不足の解消や安全性の確保、生産性向上など、製造現場をとりまく様々な課題やテーマに対して価値を発揮する「協働ロボット」。サンワテクノスでは、メーカーと連携しながら、製造現場における課題やご要望のヒアリング、技術的なご提案、導入にいたるまで一貫した技術支援を行っております。「協働ロボット」の導入をご検討されている企業様は、ぜひお気軽にお問合せくださいませ。
まずはお気軽にご相談ください
お客様の課題やご希望に対して柔軟にお答えします。

この記事を書いた人
役職名
マーケティングディレクター
小田一樹
入社1年目で物流部門へ配属となったのち、アカウント営業として8年間、FA機器・通信機器・医療機器・インフラ設備といった多様な業界のお客様へ、電子部品やFAシステムの営業活動を行ってきました。培ってきた知識をもとに、ものづくりに携わる方々のお役に立てる情報をご提供いたします。
